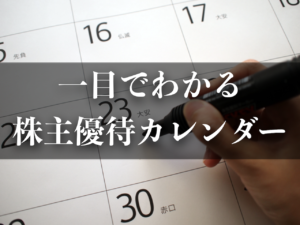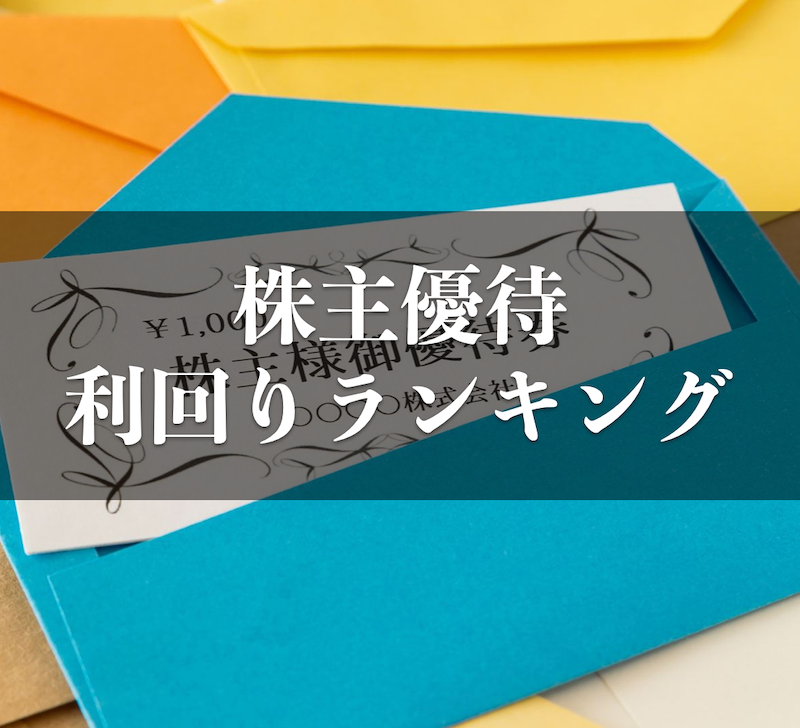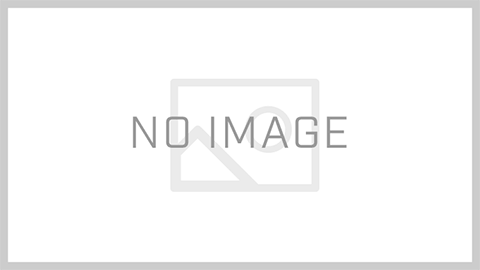今日も日本株でおトクな銘柄を探していきましょう。
今回は富士ソフト(9749)の株主優待と配当について分析していきたいと思います。
| 富士ソフト(9749) | |
| 何がもらえる? | 自社ソフトなど |
| いつ買えばいい? | 2023年12月27日 (年1回) |
| いくら買えばいい? | 約80万円 (100株) |
| 配当金は? | 13,700円 (100株) |
| 優待と配当の合計利回り | 2.02% |
富士ソフト(9749)の株主優待の内容
まずは、富士ソフト(9749)の株主優待の内容です。

富士ソフト(9749)の株主優待は①年賀状ソフト「筆ぐるめ」Windows版(DVD) or ②しいたけ詰合せです。
①は「たのしく・かんたん・きれい」をコンセプトにしている、パソコン初心者でもかんたんに使えることで評判の年賀状ソフトです。
国内の主要パソコンメーカーのパソコンにプリインストールされており、導入実績 No.1の年賀状ソフトのようです。
②は富士ソフトグループとして農業の空洞化及び地方創生に寄与するべく、当社特例子会社 富士ソフト企画株式会社が、福島県耶麻郡西会津町で、ITによる新しい農業と障がい者就労フィールドの2つをテーマとして生産しているしいたけです。
「全国サンマッシュ生産協議会」が主催する品評会にて、5年連続(2016年から2020年)で金賞を受賞しているようです。
保有株数が100株以上の株主全員がもらえます。
年に1回、12月末日時点の株主に配布されます。
ちなみに、「筆ぐるめ」Windows版(DVD)は2,480円の商品です。
富士ソフト(9749)とはどんな会社?
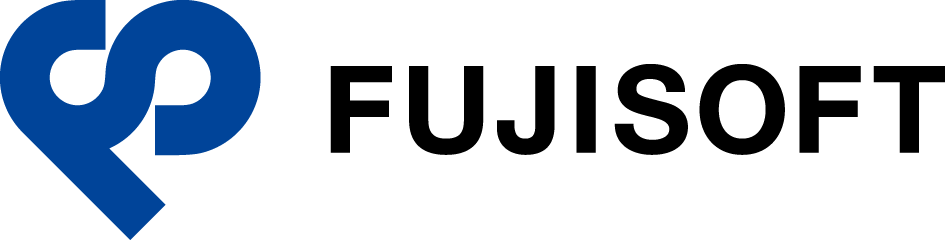
富士ソフト株式会社(ふじソフト、FUJISOFT INCORPORATED)は、神奈川県横浜市中区に本社を置くソフトウェアの開発・販売、システムインテグレーションなどを行う企業。資本的には、どの企業グループにも属さない独立系である。
野澤宏が自宅で1970年に設立した大手独立系ITソリューションベンダー。
富士ソフトはグループ全体で1万人を超える技術者を擁する。
設立から17年後の1987年12月に株式上場している。
銀行・証券・生損保などの金融系や製造、医療、文教などの業務系システムの開発と構築を行う。
また近年、筆ぐるめ、PALRO、moreNOTE、みらいスクールステーションなどプロダクトサービスも展開しているほか、通信機器の製造も行っている。
富士ソフトが主催し、1989年より開催(初年はプレ大会)されている「ロボット相撲」は、参加者が自作したロボット力士を技術とアイディアで戦わせる競技である。
全国大会には高校生の部と全日本の部があり、全日本の部は両国国技館で開催されている。
また、現在では世界各国で大会が開催されるに至っている。東証プライム。
1970年設立。従業員数(連結)は14,956人。
売上高は2,578億9,100万円。
純利益は91億3,000万円。
純資産は1,429億6,800万円だ。
(2021年時点)(参考:ウィキペディア)
富士ソフト(9749)の株主優待はいくらでもらえる?
現在の富士ソフト(9749)の株価は、7,950円(2023年4月時点)です。
100株だと「約80万円」で購入できます。
ただで優待だけ受け取ることのできるクロス取引の場合は、富士ソフト(9749)の株を購入するのに必要な手数料と信用取引の手数料920円がかかります。(SBI証券の場合)
クロス取引についてはこちら
約80万円の投資をして、もらえる優待が年間2,480円相当なので、優待利回りは0.31%です。
物足りないですね。
具体的に権利日はいつ?
株主優待の基準日は、12月末日です。
基準日の株主名簿に記載されている株主に配布されるようです。
実際の権利日は、2023年12月27日なので、この日までに購入をすれば優待をもらうことができます。
クロス取引(株主優待タダ取り)をする場合、12月27日の権利日の前日に注文をして、権利付与後の12月28日に現渡決済すればOK。
一目でわかる株主優待カレンダーはこちら
富士ソフト(9749)の配当は?
次に、配当目的の投資として考えた場合の富士ソフト(9749)は魅力的かを見ていきましょう。
富士ソフト(9749)の配当利回りは、1.71%だ。
100株、約80万円投資したら年間13,700円。
500株、約400万円投資したら年間68,500円がもらえます。
配当も少ないですね。
配当の基準日は?
富士ソフト(9749)の配当の基準日は12月末日です。
実際の権利確定日は、2023年12月27日なので、この日に株を保有していると配当がもらえます。
最後に富士ソフト(9749)の株主優待と配当をまとめてみると
優待と配当合わせて利回りは2.02%です。
うーん、正直良いところがないですね。
必要投資額も高いし、もらえる優待の魅力もそれほどです。
残念ですが、次に行きましょう。
これから株式投資を始めてみようと思われている方は、是非以下の記事も併せて読んでみて下さい。
証券会社で迷うなんて時間の無駄!株を始めるならSBI証券にした方がいい理由